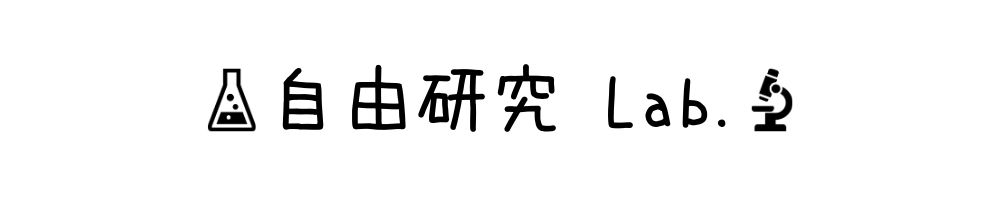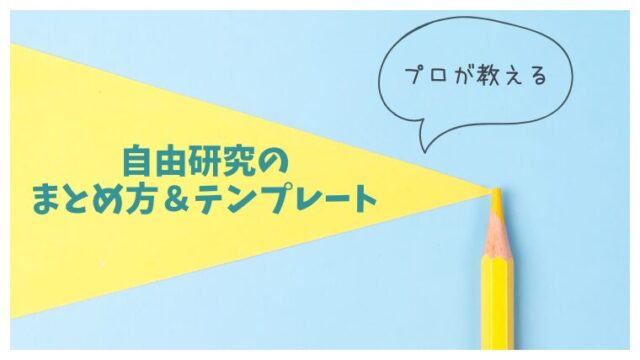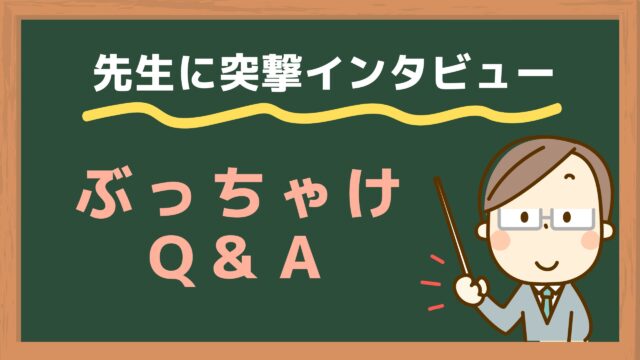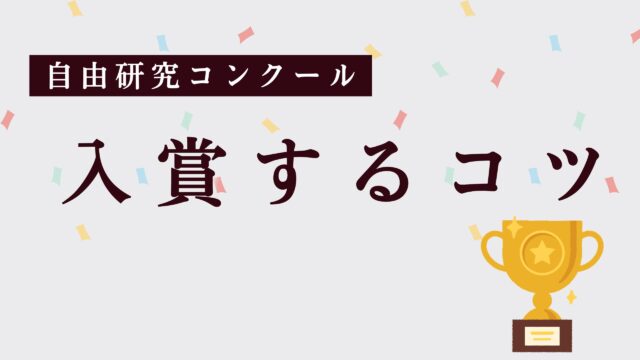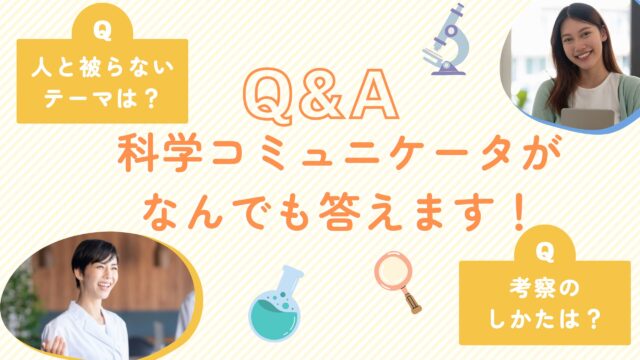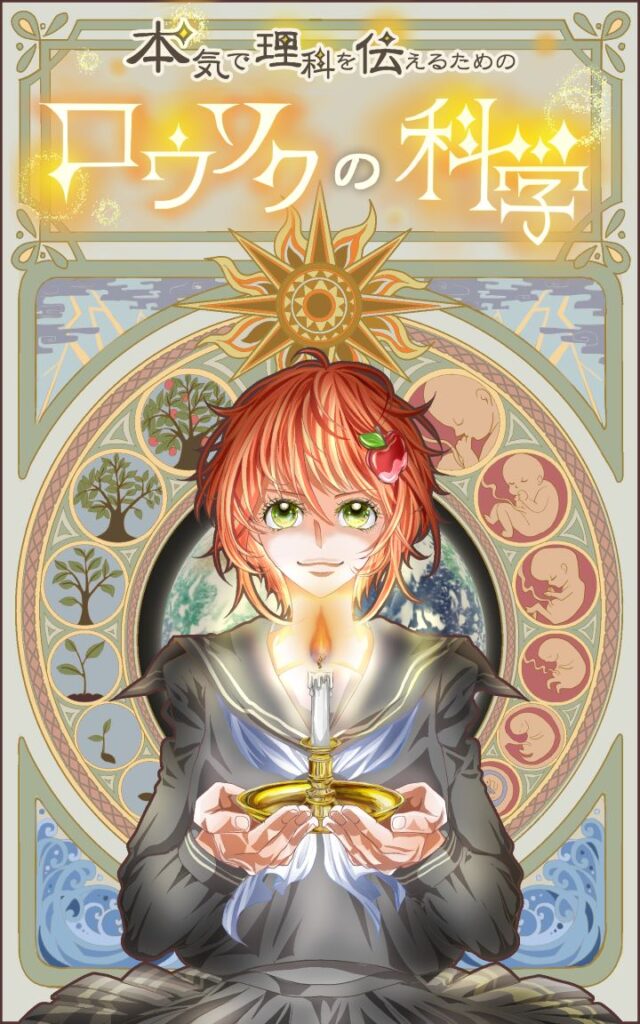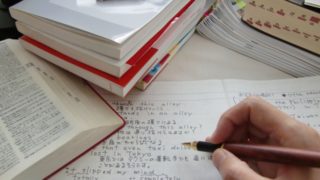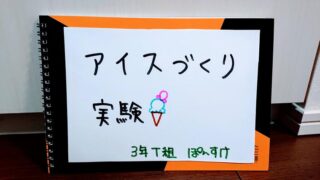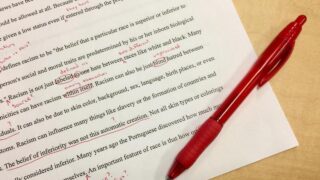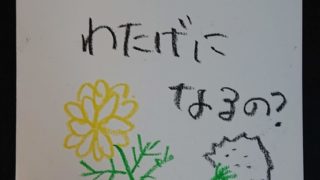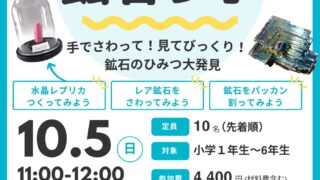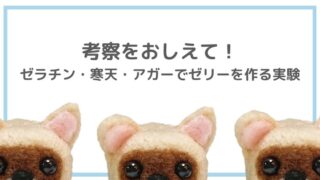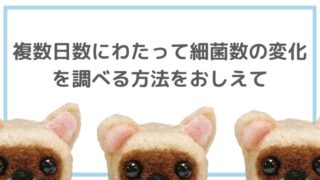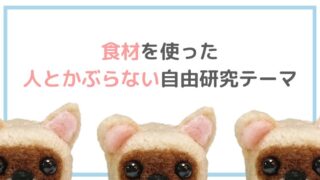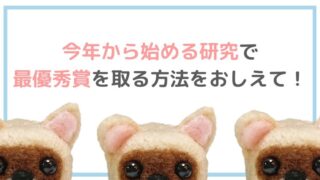【コンクール向け】自由研究レポートの基本
このページでは自由研究レポートの基本的な書き方をまとめています。
まずは、これを見て、書けるところだけ書いてみてくださいね。
空欄あっても大丈夫です!
絶対に守るべき『文章の形式』
実験レポートには絶対に守らなければいけない「文章の形式」があります。
なので、レポートの各項目の前に、まずは、文章の形式をご紹介していきますね。
文字は大きく
レポートを書くとき、老眼の人でも簡単に読める文字サイズにします(審査員が高齢な場合が多い)。
具体的には11pt以上にしてください。
文末は「ある」「である」「だった」
作文を書くときには「です」「ます」「ました」をよく使うと思います。
レポートでは、間違い。
レポートでは・・・
・「ある」
・「である」
・「だった」
を使います。
具体例▼
悪い例)「塩の結晶を作りました。」
良い例)「塩の結晶を作った。」
理科の実験レポートは、事実を書いて報告する書類です。
先生に向けて書くから「丁寧な言葉の方がいいかなぁ」って感じるかもしれませんが、気にしなくてOK。
「である」調で書いてくださいね。
1つの文章はとにかく短く
もう1つ絶対に守らなくてはいけないことは「1つの文章を短く書くこと」。
ためしに次の文章を読み飛ばしてください。
「モールで塩の結晶を作ったら、塩のつきかたがまばらで、観察してみると、糸の結び目に塩がいっぱいついていて、でこぼこしてる方が塩がつきやすいのかなと思った。」
・・・正直、読みたくない!!!
レポートは「報告書」なので、読んでもらう相手がいます。
だからこそ、読みやすい文章を書くことがお作法です。
具体的に1つの文章に何文字とは決まっていませんが、「とにかく短くしてやるぜ!」と意識してみてください。
良い例▼
「モールで塩の結晶を作ったら、塩のつきかたがまばらだった。観察してみると、糸の結び目に塩がいっぱいついていた。でこぼこしている方が、塩の結晶がつきやすいのかな?と思った。」
▼まとめ▼
・文末は「ある」「である」「だった」にする
・1つの文章をできるだけ短くする
主語と述語のねじれはNG
これはちょっと難しいけど、ぜひチェックしてほしいてお話。
主語と述語のねじれとは?
「主語と述語が対応していない文章のこと」
例)
悪い例:私の研究テーマは、水を調べた
※主語はテーマ、述語は調べた。「水は調べることができない」からダメ。
良い例:私の研究テーマは、水である。
主語と述語があっていると、グッと読みやすい文章になります。
でもでも、「主語と述語にねじれ」気づくのはすっごく難しい!!!
※ここだけの話、私もしょっちゅうやらかします・・・
初めてレポートを書くときは、気にしなくていいよ!
保護者の方がレポートを読んでみて、気になる部分がございましたら、お直しいただけますと幸いです。
表紙(タイトル)の書き方
表紙に絶対に書かなきゃいけないのは・・・
・タイトル
・学校名
・学年&クラス
・名前
です。
表紙の具体例
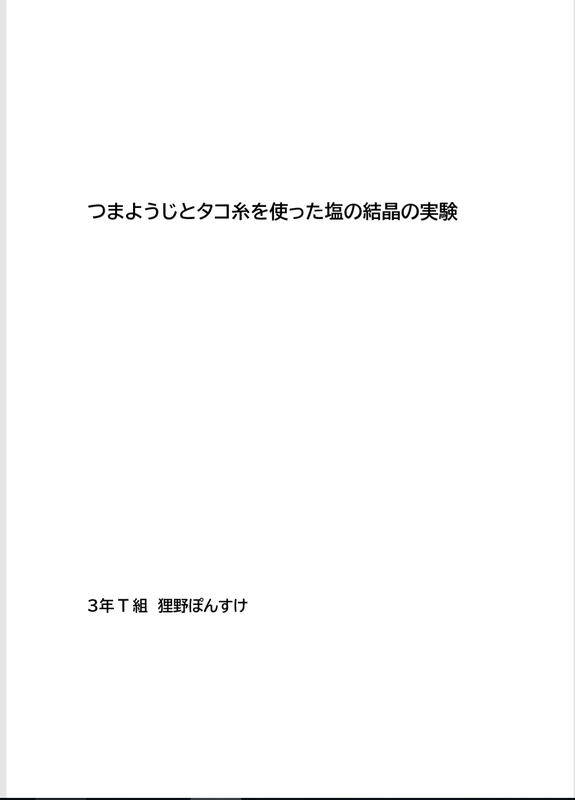
次は、「実験の動機」の書き方をお話していきます。
「動機」の書き方
自由研究レポートには必ず、実験の動機が必要です。
まずは、実験の動機って何?という解説です。
『動機』とは、「実験をやりたくなった理由」を書く項目。
具体的には・・・
1)今までに気づいたこと=知識
2)得られた知識から不思議に思ったこと
を書く。
ためしに、先ほど紹介した「なぜ久能海岸は吉浜海岸のように足跡がくっきりと付かないのか?」の動機を見てみます。
祖母の家がある神奈川県湯河原町の吉浜海岸によく散歩に行き、貝やきれいなガラスを拾った。
砂浜には、たくさんのサーファーの足跡が付いていた。
弟がサーファーの足跡をたどって遊んでいたが、足跡は海まで深くくっきりと付いていて驚いた。
砂浜には、犬やカラスなど動物の足跡もくっきり付いていた。
しかし、家の近くの静岡県静岡市の久能海岸で足跡を付けようとしたら、ほとんど付かなかった。どちらも砂でできた海岸なのに、なぜ久能海岸は吉浜海岸のように足跡がくっきりと付かないのか、疑問に思ったことが研究を始める動機になった。
「なぜ久能海岸は吉浜海岸のように足跡がくっきりと付かないのか?」より引用
↑の文章を読んでみると・・・
1)今までに気づいたこと=知識(黒い太字)
2)得られた知識から不思議に思ったこと(青い太字)
この文章を読んでみると「実験をやりたくなった理由」がわかりますね。
余談ですが、「自由研究の評価ポイントは?先生に直撃インタビューしてみた」でご紹介したように、コンクールに入賞するくらいに、ものすごく評価の高い自由研究をするには、どれだけ『動機』を語れるかが重要です。
それくらい、動機はとても大事な項目。
ぜひ、あなたが本当に気になったことや「研究対象への愛」を熱く語ってくださいね。
▼動機のまとめ▼
『動機』とは、「実験をやりたくなった理由」を書く項目。
具体的には・・・
1)今までに気づいたこと=知識
2)得られた知識から不思議に思ったこと
を書く。
動機の具体例

次は、実験方法の書き方です。
実験方法の書き方
実験方法では、実際にやったことを書きます。
具体的には・・・
実験方法で書くこと▼
1)「実験方法」というタイトル
2)実験で使った道具
3)実験の手順
を書きます。
書く順番は「タイトル→実験で使った道具→実験手順」です。
これだけ書くと難しいですが・・・要するに、料理のレシピと一緒です。
例えば、目玉焼きをつくるとします。
【タイトル】目玉焼きつくり
【道具】卵・油・フライパン
【手順】
1)フライパンを熱して、油を入れた
2)卵をフライパンに入れた
実験方法もこんな風に書いていきます。
次は、1)実験で使った道具と2)実験の手順の書き方を順番に説明していきますね。
実験で使った道具を書く
まず、実験で使った道具を書くときは、箇条書きしてください。
もし、道具の写真を撮影したら、一緒に掲載するとわかりやすいです。
実験手順を書く
実験手順では、やったことを書いていきます。
ここで必ず押さえてほしいのは・・・
手順は「過去形※」で書く
※語尾を「だった」にする。
です。
もし、実験中の写真を撮影しているなら、ぜひ盛り込んでください。
また、手順が読者に伝わりやすいように、手順には番号を振ってください。
注意点)やったこと「だけ」を書く
実験手順を書くときに、注意点があります。
・「気づいたこと」を書いちゃダメ!
・「思ったこと」を書いちゃだめ!
ちょっとわかりづらいので、目玉焼きを例に挙げていきます。
・手順の悪い例その1▼
フライパンに油を引いた。卵をフライパンに入れたら、卵が固まってきた。
→「卵が固まってきた」のは気づいたこと。手順に書いてはダメ。
・手順の悪い例その2▼
フライパンに油を引いた。油がはねて熱かった。
→「油がはねて熱かった」のは思ったこと。手順に書いてはダメ。
手順は、やったことだけを淡々と書いてくださいね。
実験方法のまとめ▼
実験方法で書くことは・・・
1)「実験方法」というタイトル
2)実験で使った道具
3)実験の手順
実験手順を書くときの【注意点】▼
・手順は「過去形※」で書く
・手順に「気づいたこと」や「思ったこと」を書いちゃだめ!
方法の具体例
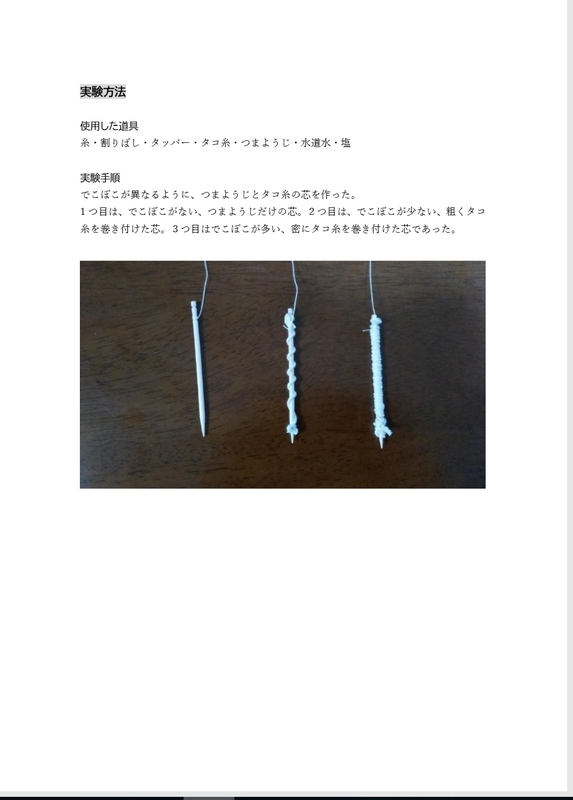
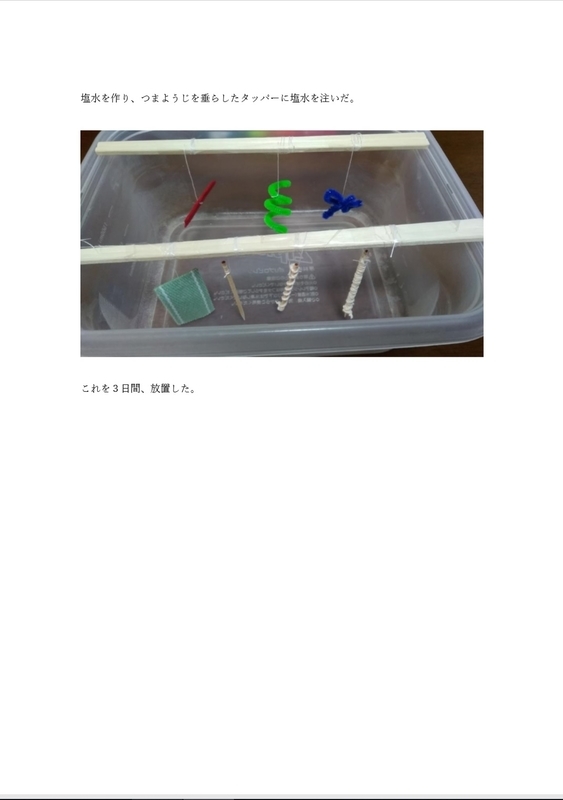
実験結果の書き方
実験結果では、観察したことを書きます。
具体例として、目玉焼き作りを実験レポート風に書いてみます。
【タイトル】目玉焼き作り
【実験方法】
・道具:卵、油、フライパン
・手順:フライパンを熱して、油を入れた。次に、卵をフライパンに入れた。
【実験結果】
フライパンを熱したら油がはねた。卵をフライパンに入れたら、卵が固まった。
実験をやっているときに、観察したことをなんでも書いていきます。
ここでも、文章の語尾に注意点があります。
必ず「過去形」で書いてください。
▼実験方法・実験結果の違い▼
・実験方法は「やったこと」
・実験結果は「観察したこと」
▼結果の書き方のまとめ▼
・実験結果では、観察したことを書く
・注意点:語尾は「過去形(=だった)」
結果の具体例
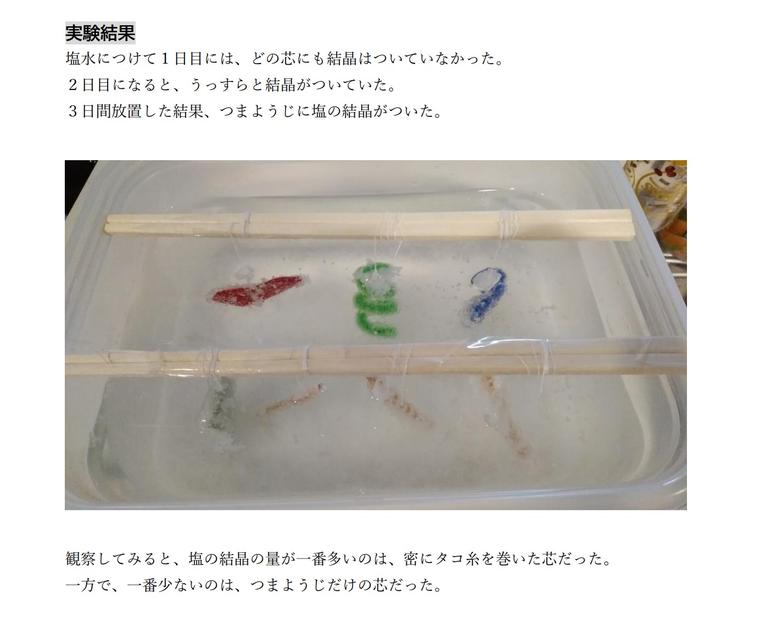
考察の書き方
考察では「実験を観察して、気づいたこと」を書きます。
もう一度、目玉焼きを例に話していきます。
【タイトル】目玉焼き作り
【実験方法】
・道具:卵、油、フライパン
・手順:フライパンを熱して、油を入れた。次に、卵をフライパンに入れた。
【実験結果】
フライパンを熱したら油がはねた。卵をフライパンに入れたら、卵が固まった。
【考察】
油がはねると危ない。
洗ったばかりのフライパンだから、水がついていたのかもしれない。
次からは、フライパンをよく拭いてから目玉焼きを作ろうと思う。
実験結果で起こったことを見て、感じたことや気づいたことを書いていきます。
▼方法・結果・考察の違い▼
・実験方法は「やったこと」
・実験結果は「観察したこと」
・実験考察は「観察して、気づいたこと」
考察に感想を書いちゃダメです!
考察のあとに「感想」という項目を作ってください。
▼考察のまとめ▼
・考察では、観察して気づいたことを書く
・感想を書きたい場合は、「感想」という項目をつくる
考察の具体例
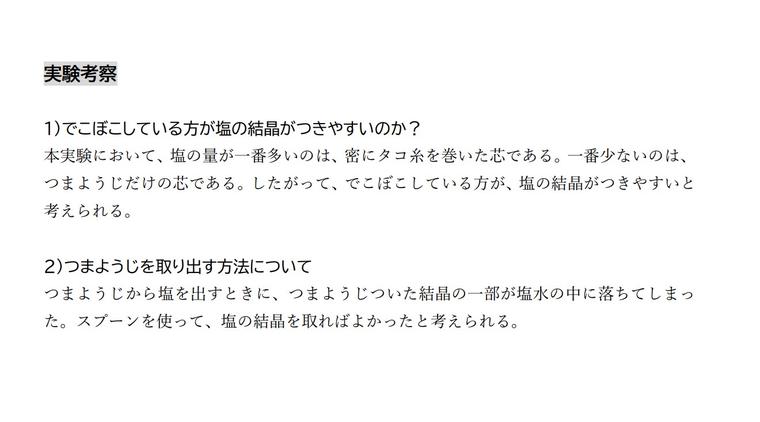
ここまでお疲れ様でした。
最後に、参考文献の書き方を解説していきます。
参考文献の書き方
そもそも参考文献ってなんでしょう?
学校でも、あまり教わらない項目だと思います。
そこで、参考文献の書き方の説明に行く前に、「参考文献とは何か?」にお答えしていきます。
参考文献ってなに?
まずは、参考文献の説明。
参考文献とは、レポートを作ったときに、参考にした本やウェブサイトのこと
です。
もし、お手元に漫画や小説があったら、終わりの方のページを見てみてください。
参考文献が掲載されている場合があります。
レポートを含め、作品を作るときに参考にしている本やウェブサイトがあったら、必ず参考文献としてまとめます。
参考文献のテンプレ
参考文献の書き方を具体的にお話していきます。
まずは、テンプレをご紹介。
参考文献テンプレ▼
本:著者名、『タイトル』出版社名、発行年
ウェブサイト:著者もしくはサイト名「記事タイトル」、(URL、閲覧日:日付)
具体例▼
本:科学編集室、「小学生の自由研究 科学編 改訂版 (学研の自由研究)」学研プラス、2012年
ウェブサイト:自由研究Lab.「【塩の結晶】つまようじ&タコ糸で「オリジナル自由研究」!やり方をご紹介(https://www.ziyukenkyulab.com/entry/shio_kesyou_tsumayouzi、閲覧日:2020年6月14日)
実は・・・参考文献の書き方に決まりはありません。
自由研究だけでなく、プロの研究者が書く論文でも「参考文献の書き方は、絶対コレ!」という書き方はないんです(論文を投稿する雑誌によって違います)。
そこで、今回の記事では、もっともシンプルなテンプレをご紹介しました。
もし、学校や自由研究コンクールで参考文献の書き方の指定があったら、そちらに合わせてください。
余談「なんで参考文献って必要なの?」
余談です。
ここまで、参考文献は、必ずまとめなきゃいけないとお話していきました。
これには理由があります。
参考文献を書く理由は、「私の自由研究はパクッてない」と証明するため
です。
もう少し詳しく知りたい方は「自由研究レポートで「参考文献」はなぜ必要?」を読んでみてください。
▼参考文献の書き方▼
・参考文献とは、参考にした本やウェブサイトのこと。
参考文献テンプレ▼
本:著者名、『タイトル』出版社名、発行年
ウェブサイト:著者もしくはサイト名「記事タイトル」、(URL、閲覧日:日付)
参考文献の具体例
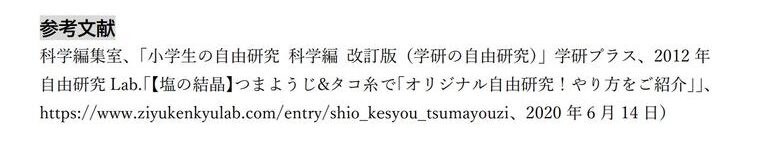
お疲れ様でした。以下がこれまでのまとめです。
(概要)『実験レポートの書き方』
▼実験レポートの構成▼
1)表紙
2)動機
3)実験方法
4)結果
5)考察
6)参考文献
文章の形式▼
・文末は「ある」「である」「だった」にする
・1つの文章をできるだけ短くする
・主語と述語のねじれはNG
表紙の書き方▼
・表紙に書くことは「タイトル・学校名・学年・名前」
・実験で何をやったかわかるタイトルにする
・タイトルの決め方がわからなかったら「使った道具と実験内容をくっつける。そのあと『実験』と書く」
動機の書き方▼
・『動機』とは、「実験をやりたくなった理由」を書く項目
動機では・・・
・今までに気づいたこと
・気づいたことから不思議に思ったこと
を書く。
実験方法の書き方▼
実験方法とは、「実際にやったこと」を書く項目
書く内容▼
・「実験方法」というタイトル
・実験で使った道具
・実験の手順
※実験手順を書くときの【注意点】▼
・手順は「過去形※」で書く
・手順に「気づいたこと」や「思ったこと」を書いちゃだめ!
結果の書き方▼
・実験結果とは「観察したこと」を書く項目
・注意点:語尾は「過去形(=だった)」
考察の書き方▼
・考察では「観察して気づいたこと」を書く
・感想を書きたい場合は、「感想」という項目をつくる
参考文献の書き方▼
・参考文献とは、参考にした本やウェブサイトのこと。
参考文献テンプレ▼
本:著者名、『タイトル』出版社名、発行年
ウェブサイト:著者もしくはサイト名「記事タイトル」、(URL、閲覧日:日付)